
介護ニュース
常勤換算とは? 介護報酬の算定に必須となる常勤換算の計算方法を正しく理解しよう
介護保険法では、人員配置基準を満たしているかを「常勤換算」で計算します。介護報酬の算定では非常に重要な計算方法です。しかし、複雑でよくわからないと感じている人も多いでしょう。そこで今回は「常勤換算」について詳細に解説します。
常勤換算とは?
その事業所で働いている人の平均人数を表すための計算を「常勤換算」といいます。介護保険法上で決められている施設の人員基準を満たしているかを同一基準で計算するための計算式です。
ここでいう常勤とは、従業員の実際に働いている時間がその事業所のフルタイム労働時間に達している場合を指します。雇用契約上でフルタイム労働となっていれば、正社員でも契約社員などの非正規職員でも常勤として計算します。例えば、その事業所のフルタイム労働時間が週40時間となっている場合、週30時間働く正社員は非常勤となりますが、週40時間働く契約社員は常勤としてカウントします。ただし、その事業所の常勤時間数が週32時間を下回る場合には、週32時間が基準時間となります。
介護保険法で決められている人員配置基準は、事業所の種類によって違います。以下に、事業所における介護職員の人員基準を見ていきましょう。
訪問介護事業所の常勤換算
訪問介護事業所の訪問介護員は、以下の資格を持つ者が常勤換算2.5人以上必要です。
- 介護福祉士
- 介護職員実務者研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者
- 旧介護職員基礎研修修了者
- 旧ホームヘルパー1級および2級
- 看護師および准看護師
- 生活援助従事者研修修了者
なお、この計算にはサービス提供責任者も含めます。
通所介護(デイサービス)における常勤換算
通所介護では、利用者が15人までは専従の介護職員が1人以上必要です。15人から1人でも利用者が増えれば、5人おきに専従1人以上が必要となります。
通所リハビリにおける常勤換算
通所リハビリ(デイサービス)では、サービス提供時間を通じて利用者10人まで専従1人が必要です。10人を超える場合は利用者の数を10で割った数の専従者が必要となります。
この人員基準を満たさなかった場合には介護報酬が減算されます。具体的には、減算対象の月から2か月が介護報酬額30%カット、3か月連続で人員基準を満たしていない場合には50%がカットされます。人員基準違反が続くと、指定取り消しや業務停止などの行政処分が科される可能性もあるでしょう。
常勤専従を理解しよう

正しく常勤換算を行うには、常勤専従についての理解が欠かせません。この制度により、各業務に必要なリソースを最適に配分し、効率的な運営を実現できます。常勤専従の仕組みを理解することで、職場のリソース管理をより効果的に行うことができます。
介護業界における常勤専従とは、基本的にフルタイムで、特定の職種や業務に専任で従事する勤務形態を指します。これは、国の介護保険制度や事業所運営基準によって定められている条件であり、介護サービスの質を確保するために重要な概念です。この勤務形態を理解するには、常勤と専従の意味がカギになります。
前述の通り、常勤とは、事業所の就業規則で定める所定労働時間、つまりフルタイム(通常は週40時間)の勤務形態で働くことを指します。この所定労働時間を満たさないスタッフは非常勤とみなされます。ただし、所定労働時間が週32時間未満の場合は、32時間を基本とします。また、労働基準法では、特例を除き、週あたりの労働時間は40時間を超えてはいけないため、常勤スタッフは週32時間から40時間働くことになります。
次に、専従とは、特定の業務や役職に専念し、他の業務を担当しないという意味です。事業所の勤務時間内にいくつか異なる職種を担当しているスタッフは専従ではなく、兼務と判断されます。ただし、令和3年介護報酬改定によって、育児や介護のために時短勤務をする場合は週30時間以上の勤務で常勤換算の条件にあてはまるようになりました。また、自治体や事業所の規模によっては、専従の例外として兼務が認められるケースがあります。
以下の職種・役割では、法律や基準により常勤専従が条件として定められています。
- 訪問介護事業所のサービス提供責任者:利用者のケアプラン調整やヘルパーへの指示を行う「サービス提供責任者」が必要で、常勤専従として配置することが求められます(事業所の条件により、兼務でも可能なケースあり)。
- 特別養護老人ホームの生活相談員:利用者や家族との相談業務を行う生活相談員は、原則として常勤専従が求められます。
- 小規模多機能型居宅介護の管理者:管理者は常勤専従でなければなりません。例えば介護支援専門員、サービス提供責任者、看護師などは常勤専従にあたります。
これらの職種においては、利用者との信頼関係を築きやすい、緊急時の対応がスムーズ、専門性を高めやすいといったことから、常勤専従であることが重要と考えられます。常勤専従のスタッフ配置は介護事業所を運営する上で大きなポイントであり、適切な人員配置により利用者へのサービスの質の向上が期待できます。
常勤換算の計算方法を覚えよう
常勤換算の基本的な計算方法は次の通りです。
「各従業員の1か月の勤務合計時間÷事業所の定める常勤職員の勤務すべき時間数=常勤換算人数」
ここで注意すべきは、「事業所の定める常勤職員の勤務すべき時間数」です。常勤時間数を週32時間未満に設定している事業所の場合は、週32時間を正しく常勤として計算します。そして、計算は1か月(4週間)を基本とします。
それでは、以下の条件で具体的な計算方法を見ていきましょう。
- 常勤者が勤務すべき時間数は週40時間、4週間で160時間
- 非常勤Aさんの勤務時間は4週間で128時間
- 非常勤Bさんの勤務時間は4週間で96時間
この条件を計算式に当てはめると、「(128時間+96時間)÷160時間=1.4」となり、この場合の常勤換算人数は1.4人となります。
常勤者の場合は、勤務延時間数を算入することができます。勤務延時間数とは、勤務表上事業に関わるサービスの提供や準備時間等として明確に位置づけられている時間です。労働基準法に定められている最低限の休憩時間も含まれます。ただし、算入の上限は常勤者が勤務すべき勤務時間数までです。
上記の条件に4週で180時間勤務する常勤Cさんを加えて計算してみましょう。Cさんは180時間の勤務時間ですが、算入できるのは常勤者の勤務時間数となるので160時間で計算します。AさんとBさんにCさんを加えた常勤換算計算は以下の通りです。
(128時間+96時間+160時間)÷160時間=2.4
常勤換算の注意点:有休や産休などの取り扱いをしっかり覚えよう
常勤換算では、有休や出張の取り扱いは常勤者か否かで計算が変わります。常勤者の場合は、有休や出張も勤務しているとして計算に含まれます。しかし、非常勤の場合には算入できません。ただし、常勤者でも長期出張や休暇が暦の上で1か月を超えたときには計算から除外します。産休や育休も長期休暇に該当しますので、基本的には算入できない点に注意しましょう。
産休や育休明けで時短勤務している場合には、次の条件を満たしている場合に限り、常勤の所定労働時間を週30時間とすることができます。
- 雇用契約で常勤職員として雇用されていることが明らか
- 短時間勤務に従事している時間が週30時間を下回らない
- 法人の就業規則に短時間勤務に関わる勤務時間が明記されている
パートタイム労働者の常勤換算と103万の壁
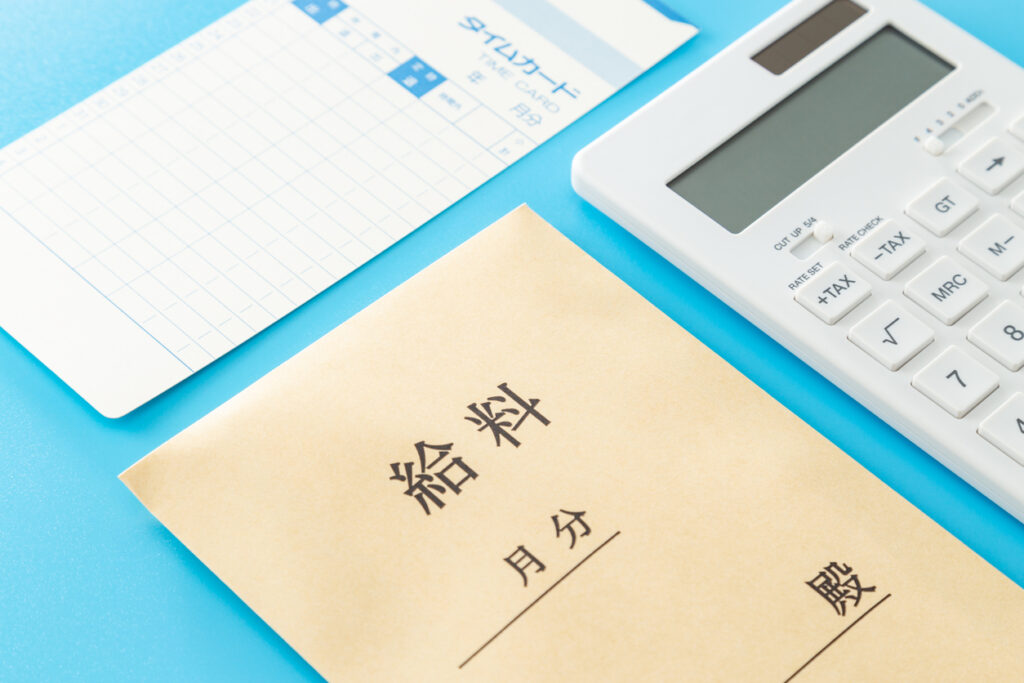
パートタイムで働く場合、勤務時間によって常勤・非常勤の扱いが変わることを理解しておくことが大切です。特に、103万円の壁を超えると、社会保険や雇用保険の加入が義務付けられるため、手取り収入に影響が出る可能性があります。安定した福利厚生を提供するためには、常勤としての扱いも一つの選択肢ですが、それぞれのライフスタイルや収入のバランスを考慮することが重要です。
介護報酬の算定では、パートタイム人員配置の常勤換算の計算も必要になります。パートタイム労働者の常勤換算とは、パートタイム労働者の勤務時間をもとに、介護事業所全体で常勤職員に相当する人数に置き換えて計算する方法です。例えば、所定労働時間が週40時間の事業所の場合、週30時間働くパート職員は「30時間÷40時間=0.75」となり、常勤に対して「0.75人分」として換算されます。この計算は事業所の報酬や基準に影響しますが、パート職員個人の収入には直接影響することはなく、あくまで実際に働いた時間にもとづきます。
パートタイム労働者の常勤換算は、介護報酬算定の基準をクリアするために重要な役割を果たします。特に、加算取得や基準人員の確保においては、パートタイム労働者を有効に活用しつつ、正確に計算することで適切な報酬を確保できます。
ここで、パートタイムでの雇用について気になるのが、前述の通り昨今話題となっている「103万の壁」ではないでしょうか。103万の壁とは、年間収入が103万円を超えると本人の所得税が発生し、家族の扶養控除から外れるという税制上の境界線です。加えて、「106万の壁」を意識して働くパートタイム労働者も多いと思われます。106万の壁は社会保険料の負担が増加するという年収のボーダーラインです。
では、介護事業所の常勤換算が、年間収入103万円や106万円以内で働くことを希望するパートタイム労働者に影響することはあるでしょうか? まず、考えられるのが、事業所が常勤換算基準を満たすために勤務シフトを増やすことで、パートタイマーの労働時間が増加し、これらの金額を超える年収になる可能性です。一方、年収103万円または106万円以下に抑えるために勤務時間を削減する場合もありますし、配置基準維持のために勤務時間管理が厳格化される可能性があり、パートタイマーの自由度が制限されることがあるかもしれません。したがって、事業所としては、スタッフ本人と相談しながら勤務時間を調整することが大切です。また、壁を超える場合は、税金などの負担を考慮した上での働き方を計画する必要があります。
最近では、103万の壁廃止が議論されています。介護現場はパートタイムや非正規で働く人が多いものの、この年収の壁の範囲内で働きたいという傾向が強く、雇用側としては労働力確保の面からは難しいものがありました。そのため、103万円の年収の壁撤廃が実現すれば、人手不足が深刻な介護業界では、既存スタッフの勤務時間が増え、シフトが組みやすくなるなど、期待が寄せられています。
正しい介護報酬算定は常勤換算の理解から
人員配置基準は違反すると罰則があります。場合によっては、行政処分が科されることもあるでしょう。常勤換算をしっかり理解しておくことは、事業所にとっても大きなメリットとなります。常勤換算をしっかりと理解し、介護報酬の算定を正しく行うようにしましょう。
参考:



 マスク着用だからこそ気をつけたい介護職の熱中症
マスク着用だからこそ気をつけたい介護職の熱中症  ホスピタリティとは? 介護の質向上のための大原則と3つのステップを知ろう
ホスピタリティとは? 介護の質向上のための大原則と3つのステップを知ろう  最新機器を使って転倒に関する課題を解決!高齢者の転倒を防ぐ新しい試み
最新機器を使って転倒に関する課題を解決!高齢者の転倒を防ぐ新しい試み